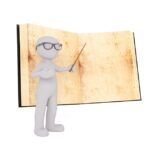日本における3月決算企業の多さゆえ、
6月は株主総会の季節。
企業と資本の関係性を象徴的に映し出すこの月に、
ふと考えることがあります。
私自身が属する企業も、
形式的とはいえ株主総会を実施したようです。
「シャンシャン総会」
という言葉に代表されるように、
かつての株主総会は、
意思決定のプロセスをなぞるだけの“儀式”に過ぎない場面も多かった。
しかしここ数年、
特にガバナンス改革と資本効率重視の機運の中で、
その空気が確実に変わりつつあると感じています。
物言う株主の登場、
東京証券取引所によるPBR改善要請、
機関投資家によるスチュワードシップ・コードの実践——。
こうした圧力や潮流が企業の内部にも外部にも作用し、
「経営と所有の対話」
の前提を着実に揺さぶっているのです。
考えてみれば、
株主総会とは経営と資本提供者とが年に一度、
制度として公に交わる舞台装置です。
それは単なる決議機関ではなく、
企業の存在意義・持続性・資源配分の妥当性を共有・再定義するためのプラットフォーム。
いわば、
資本主義という枠組みにおける
「制度的対話」
のひとつの完成形と言えるかもしれません。
株主は企業の“所有者”であると同時に、
“批評者”
でもあります。
そして、
その視線が企業の振る舞いに影響を与え得るという意味で、
株主総会は単なる年中行事ではなく、
民主主義にも似た機能を内包しているのではないでしょうか。
企業の将来性を見極めるだけではなく、
資本主義そのものの在り方を考えるきっかけとして——
6月は、
そんな問いを静かに突きつけてくる月でもあります。